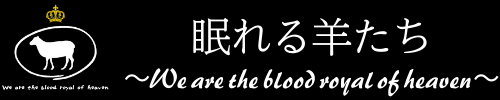眠れる羊くん
眠れる羊くん K
K~ 聖書は信じるに値するか? No.16 ~
「聖書を読むことの面白さ」について、お伝えしています。
「面白さって言うけど……、聖書って実際どんなこと書いてあるの???」という方は、
『【要約】聖書ってどんな内容? あらすじを分かりやすく解説』をご覧になってみてください。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
みなさんの多くは、「聖書って面白いよ~」と聞いても、
「宗教やってる人には、そりゃ面白いんでしょうよ」
くらいに思われる方が多いのではないでしょうか?
しかし私は、聖書を「宗教の本」としておすすめしているのではありません。そうではなく「一般の読み物」として読んでも面白いんだよ、ということを知ってほしいな、と思ってるのです。
今回は、聖書を読む楽しさを「4つの魅力」に分けて、ご紹介してみたいと思います。
【神の言葉の平原】 ― kami no kotoba no heigen ―
はたから見れば、このような何もない平原を散歩するなんて、時間を浪費するだけの、ひどく退屈なことに見えるでしょう。
一方、散歩を楽しんでいる人たちの視点から見ると、その見え方はまったく違っているものです。
私たちを先導するかのようなダイナミックな雲、神が私たちの目を楽しますために創造された色とりどりの花々、
その枝をチョコチョコと器用に歩き回る「ナナホシテントウ」の愛らしさ、陽の光を受けて淡緑色の光を宿す新芽のゆらぎ、等々、
はたからでは想像できない面白さを満喫しているのです。さあ、この「聖書の世界」の奥深い楽しみを見出だせるよう、いくつかの点に着目してみましょう。

※栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
ズバリ、聖書のここが面白い! | 奥深いその4つの魅力

 眠れる羊くん
眠れる羊くん K
K 眠れる羊くん
眠れる羊くん
そう、たしかに面白くない部分もたくさんあるのです。
それは始めに断っておく必要があると思います。そうでないとウソになってしまいますから。
ただ、そういった部分の多くが面白くない理由の1つとして「意味が分からないから」ということが挙げられます。
逆に言えば、意味が分かってくるにつれ、面白い部分が増えていくのです。聖書とは、それだけ奥深い読み物だとも言えます。
 K
K旧約聖書は「歴史物語」として、ふつうに面白い
聖書に馴染みのない日本人にとって、「聖書」=「難解な哲学書のような本」というイメージがあるかもしれませんが、実を言うと、旧約聖書の大部分は「物語風」に書かれています。
つまり、小説を読むような感じで読めるわけです。しかも、
- 奴隷であったイスラエル民族の、エジプトからの大脱出劇。
- 名も無い羊飼いであったダビデが、王になる物語。
- ソロモン王の栄華とつまづき。
- 繰り返し「神の教え」を破り、痛い目に合いまくるイスラエルの民。
- 命をかけて民に訴え続ける、預言者たちの苦悩と迫害。
などなど……、すべて実話をもとに記録されたものなので「フィクション物」とは一味違った楽しみがあるのもポイントだと言えます。
私の1番のおすすめは、メシアを輩出する家系とも預言された「ダビデ王」の物語を描いた「サムエル記 上下」です。
ネット上でも無料で読めますから、この「サムエル記」の部分だけでも読んでみてはいかがでしょうか?
また、見出しでは「旧約聖書」と題していますが「新約聖書」の中の
- 4つの福音書。
- 使徒言行録(使徒行伝、使徒の働き)。
も、物語調で書かれていますので、小説を読む感覚で、面白く読めるかと思います。
聖書には「預言の書物」としての面白さがある
この点については、これまでの記事で、かなり突っ込んでお話してきましたので、ここでは割愛しますが、まだ読まれていないという方は、
『預言とは何なのか? | 人類に突きつけられた神からの挑戦状』という記事をご覧になってみてください。
聖書が、たんなる「歴史物語」ではなく「預言の書」であることが、お分かりいただけるかと思います。
聖書は「格言集」として読んでも面白い
旧約聖書の中には、ソロモン王の残した格言を集めた「箴言(しんげん)」という書が収録されています。
彼は、イスラエル王国の最盛期を築いた王で、
- 地位
- 名声
- 知恵
- 莫大な富
- 700人の妻
と、およそこの世で人間が手にしうる、ほぼすべての物を手にした人物でもありました。
ところが彼は、その晩年に「自分が手にしたものは、すべてむなしいものであった」と述懐しています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
あらゆるものを手にした上での言葉だからこそ、その言には「説得力」と「重み」が伴っていると言えます。
「箴言」は私たちにとって、”先人からのアドバイス”として、たいへん勉強になる書です。
このような人物が残した「格言」に耳を傾けるというのも、聖書の楽しみ方の1つなのです。
聖書は、謎が解けると面白い!
聖書を読んでいると……、
- 「――このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる」*1
- 「死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい」*2
- その頭には十本の角があり、更に一本の角が生え出たので、十本の角のうち三本が抜け落ちた。その角には目があり、また、口もあって尊大なことを語った。これは、他の角よりも大きく見えた。*3
*1 マタイによる福音書 20:16 (新約聖書 / 新共同訳)
*2 同じく8:22
*3 ダニエル書 7:20 (旧約聖書 / 新共同訳)
などの ”パッと見、意味の分からない表現 & たとえ”が、多々登場します。
このように、聖書には「パズル」や「謎解き」にも似たような要素があり、それが解けると「そういう意味だったのか」と、理解が徐々に広がり、深まっていくという面があります。
そうやって、意味深な言葉の謎が解けていくのも、聖書ならではの面白さと言えます。
まとめ
- 聖書には、たしかに面白くない部分もある。ただ、その多くは「意味が分からない」からであって、意味が分かってくると、また違ってくるものである。
- 旧約聖書の大部分は「物語」になっているため、小説を読む感覚で読める。中でもおすすめは「サムエル記」。
- 聖書が他の書物と大きく違う点は「預言」が織り込まれている点である。聖書中の「預言」に注目して読むのも面白い。
- 「富」も「名声」も手にした反面、それらを全否定した ”ソロモン王の格言”に触れてみるのも、知的好奇心を満たす面白さの1つと言える。
- 聖書中に登場する数々の「謎めいた言葉」を理解していく過程も、聖書ならではの面白さである。
いかがだったでしょうか?今回は「聖書を読む面白さ」について、簡単に4つの魅力をまとめてみました。
聖書に興味を持ってくださり、「今後、読んでみようかな」と思われている方の参考になれば幸いです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
 眠れる羊くん
眠れる羊くん『【超入門】ざっくり過ぎ!? 聖書に関する基礎の基礎』へは下のリンクから!
眠れる羊くん この記事の内容は、You Tubeでも観れるよ♪ https://youtu.be/B-31HuN_E4A https://youtu.be/PlM4jBXIxzw […]
 眠れる羊くん
眠れる羊くん