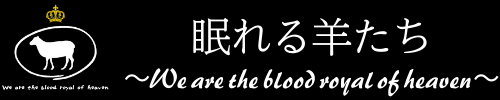復活のことを切り離して考えれば――十字架で死んで、ただ葬られただけの「神の子」など、我々に何の役に立つであろうか。
そういうことは誰も信じないであろう。
逆に復活という事実からキリストを神の子と結論することは、きわめて論理的に一貫した推理である。
もし復活が真実でないとしたら、キリスト教全体が誤謬か、錯覚に基づくばかりでなく、まさに虚偽の上に立つことになる。
『幸福論(第三部)』 ヒルティ著 草間平作 訳 岩波文庫
 K
K~ 聖書は信じるに値するか? No.23 ~
「イエスが本当に復活したかどうかの根拠」
について、お伝えしています。
「人間が死からよみがえったなんて馬鹿げた話、どうして信じられるわけ!?」
これが自然かつ、まともで健全な反応だと思います。
たしかに、他の情報を考慮せず「人間が死からよみがえった」という点だけを考えれば、これほど馬鹿げた話はないと私も思います。
ところが、その「根拠」を1つひとつ検討してゆくと、実際に復活したと考えるのが、最も理にかなった無理のない見方であるという結論に達するのです。
これから私たちは、その「根拠」について、専門家の話をうかがいながら見ていきたいと思います。
はたして「復活」はあったのか、なかったのか?
この記事を読んだあとで、あなたはどう判断なさるでしょうか?
【合わせて読みたい】
『理屈っぽく、宗教嫌いの私が、それでも聖書と神を信じる4つの理由』
さらに詳しくお知りになりたい方は、ぜひ、この書をお手にとってみることをオススメいたします。
【神の御業の丘陵】
– kami no miwaza no kyuuryou –
ようやく、丘の頂きが見えてきました。
かつて「十字架」が立てられた、かのエルサレムの丘も、このような殺伐とした景観だったのでしょうか。
足元をご覧ください。まるで、荒廃の中から息を吹き返したかのように、萌黄色の小さな芽が顔を出しています。
さあ、頂上に達する前に、私たちの旅の「要(かなめ)」に当たる部分を、この目で確かめてみましょう。
※栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
イェシュア(イエス)の復活が「事実」だと考えうる5つの根拠

 眠れる羊くん
眠れる羊くん K
K【イエス復活の根拠1】そもそも後世の人々による伝説ではない
 K
Kパウロが書簡による宣教を開始したのは、紀元40年代の後半だとされている。
⏬
福音書が書かれたのは、彼の書簡がすべて書かれた後のことである。
⏬
パウロの書簡の大部分は、50年代に書かれている。そしてそこには、”イエスの死が私たちの罪を贖うためのものであったこと”や、”復活したイエスが多くの弟子たちの前に姿を現したこと”などが、すでに記されている。
⏬
パウロの回心は、紀元33~35年頃だとされている。
⏬
回心から数年以内には、初代教会の人々がすでに信じていた信条が、パウロに伝えられたと考えられる。
⏬
つまり、クリスチャンたちの復活に対する信条は、イエスの死後、数年以内には構築されていたと言っても差し支えないことであり、40年*、あるいはそれ以上たってから伝説化されたものではない。
* 福音書の中で最も古いとされている「マルコによる福音書」は、イエスの死から約40年後に書かれたとされている。
クレイグ博士曰く……、
- 文法
- 言葉づかい
- 文章のスタイル
等の違いによって、マルコが「イエスの受難に関する部分」を、別の資料から引用したことは明白だと言います。
 K
Kこのような短期間の内に、しかも当時を実際に知る者たちが、まだ大勢いる中にあって、話が事実とはかけ離れた形で伝説化し、その内容が広く受け入れられて伝承されていったとは考えにくいと、クレイグ博士は指摘しています。
【合わせて読みたい】
『【考察】聖書の記述は信頼に値する? ペテン師のでっち上げ!?』
【イエス復活の根拠2】敵対者の「証言」が逆に復活を後押ししている
当時の風習では、十字架上で絶命した受刑者は、そのまま磔(はりつけ)の状態で放置されて鳥のえさになるか、共同墓地に投げ込まれるかでした。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん* 恩赦…… 犯罪者をゆるすこと。
【合わせて読みたい】
『十字架刑とイェシュアの死因について | 彼は、本当に死んだのか?』
イェシュア(イエス)の遺体は、ピラトの許可を得て引き取られ、墓に葬られたわけですが、クレイグ博士によれば「墓の入口」は地下にあったのだそうです。
墓の入口は、動物の侵入を防ぐため等の理由から「大きな円盤状の丸石」でふさがれました。
この丸石は、男手が2~3人必要なほどの大きさで、入口へと続くゆるやかな下り坂の小道を転がしてゆき、設置されるのだと言います。
また、この丸石を固定させるため、周りに小さな石が置かれるのだそうです。
聖書によれば、イエスを訴え「十字架刑」へと追い詰めたユダヤ教の指導者たちは「墓の番兵が眠ってしまったためにイエスの遺体が盗まれたのだ」と主張しています。
不手際があれば「重い処罰」を受けることを自覚しているはずの「数人の番兵たち」が目の前で居眠りしている内に、巨大な丸石を動かしてイエスの遺体を運び出したとするには、かなり無理があると思います。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん【イエス復活の根拠3】発見者が「女性」である事が信憑性を高めている
 K
K哲学博士。神学博士。イギリスのバーミンガム大学にて哲学博士号を取得。ミュンヘン大学にて神学博士号を取得。著者のストロベル氏曰く「イエスの復活」に関する世界最強の論客。
しかし、彼女たちは ”イエスのことを信奉していた者たち” であったのだから、その「証言」を鵜呑みにするのは、フェアとは言えないのではないか?
イエスにとって、また、彼を信じる自分たちにとって都合の良い、偏った証言を「でっち上げ」たと考えるのが妥当ではないのか?
 眠れる羊くん
眠れる羊くん当時のユダヤ社会においては、日本に住む現代の私たちには想像もできないほど、女性の地位はたいへん低いものでした。
このような背景を考えた時、墓が空であることを最初に証言したのが「女性たち」であったとされていること自体、当時としては非常識なことだったのです。
もし仮に「遺体の消失」および「イエスの復活」が、でっち上げられたファンタジーに過ぎないのであれば、最初の発見者および、その証言者は……、
- ペテロ
- ヤコブ
- ヨハネ
といった「男性の弟子たち」にしたはずであると、クレイグ博士は指摘しています。その方が、よっぽど説得力があるからです。
 K
K 眠れる羊くん
眠れる羊くんこのように、”はじめの発見者が女性たちであった” ということが、実はこの話に信憑性を加えているのです。
【合わせて読みたい】
『「聖書なんて作り話でしょ?」って思った時に読んでみる記事』
【イエス復活の根拠4】復活以外、弟子たちの不可解な行動の説明がつかない
 K
K哲学博士。南カリフォルニア大学にて哲学博士号を取得。ミズーリ大学にて化学学士号を取得。その他、神学修士号、歴史学修士号を持つ。
当時、十字架で死んだ者は神に呪われると信じられていました。
また、まさかメシアが死ぬとは、誰も考えていなかったと博士は指摘します。
それゆえ、イエスの死後、弟子たちは彼に対して抱いていた「メシアに関する希望」を完全に失い、自分たちも捕まるのではないかと恐れ、戸に鍵をかけて身を潜めていたのです。
「メシアって何??」という方は……、
『聖書とは、ひとことで言えば「メシアについての書物」である』を、どうぞ。
さらに聖書によれば、その後ほとぼりも冷めると……、
- ペテロ
- ヨハネ
- ヤコブ
といった一部の弟子たちは、もとの職業である「漁師」の仕事に戻ってしまってすらいます。
そんな彼らが、その後、突如として再び集まり、イエスがメシアであることを証言しはじめたわけです。
メリットどころか、イエスがメシアであることを証言することによって、彼らは……、
- バカにされ
- 住む場所を失い
- 鞭打たれ
- 牢獄に入れられ
- 処刑すらされた
のです。
実際に、残された11人の使徒たちの内、10人までもが、それによって命を落としています。
このように、弟子たちが、普通では理解しがたい行動に出たことを論理的に説明するためには、彼らが「復活したイエス」を、実際に目の当たりにしたのだと考える以外、他に説明のしようがないのです。
中でも、使徒の1人である「トマス」などは、他の弟子たちから、復活したイェシュアに会ったと聞かされても、
「彼の手に釘の痕を見て、私の指をその釘の痕に入れ、私の手を彼の脇に入れるのでなければ、私は信じない」
ヨハネによる福音書 20:24~25(田川訳)
とまで言っています。
 K
K
 眠れる羊くん
眠れる羊くんもともと、厳しい修行に耐えた極一部の人しか救われないという教え(=小乗仏教)であった仏教に、
大勢の者が救われる(=大乗仏教)という教えが加わったのは、このトマスの影響によるとも言われています。
使徒たちは、だまされたのでなければ、だましたのだ。
だがどちらも困難だ。ある男が生きかえったと勘違いすることなど、ありえないのだから。
――イエス・キリストは、彼らとともにいる間、彼らを支えることができた。
しかしその後で、もし使徒たちに彼が現れなかったとすれば、誰が彼らを動かしたのか。
『パンセ(上)』 パスカル 著 塩川徹也 訳 岩波文庫
もし使徒たちにとって、キリストが十字架にかけられ、墓に葬られたままで終わったならば、キリスト教を世に伝える勇気を彼らは持たなかったであろう。
使徒行伝の冒頭からきわめて明瞭にうかがえるように、このまったく異常な事実を自分で親しく経験したことだけが、ユダヤ教の祭司制に対抗して立ち上がる勇気を使徒たちに与えたのであった。
『幸福論(第三部)』 ヒルティ著 草間平作 訳 岩波文庫
【イエス復活の根拠5】彼の死後、なぜか態度が急変した者たちがいる
それは、それまでイエスが「メシア」であるとは信じていなかった者たちが、彼の死後、なぜかその考えを180度変えている、という点です。
たとえば……、
イエスの実の兄弟である「ヤコブ」は、十字架前には、彼がメシアであるなどとは信じていませんでした。
その証拠に、イエスの家族が「あの男は気が変になっている」という噂を聞きつけて、イエスを取り押さえに来ている場面があります(マルコ3:21)。
モーランド博士によれば……、
古代ユダヤ教では、ラビ自身が自分の家族に「ラビ(指導者、先生)」として受け入れられないことは非常に恥ずべきことであったことから、
上記の出来事が事実でなければ、この話を残す理由がないと指摘しています。
 K
K
歴史家の「ヨセフス」によれば、このヤコブも、イエスに対する信仰ゆえに「石打ちの刑」で殉教したと記録されています。
十字架後のヤコブの行動を説明するには、彼が「復活したイエス」を見たとする以外に、説得力のある答えが見つからないのです。
そして、それが事実であったとするならば、彼が「実の兄」の顔を別のよく似た人物と見間違う、などということはあり得ないだろうと、博士は指摘しています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
イエスのことを、私たち異邦人に伝えた立役者であるパウロは「筋金入りのファリサイ派」として、クリスチャンたちを迫害する側の人間でした。
ユダヤ教内で力を持っていた一派で、律法(聖書の教え)を厳格に守ることが特徴。「愛」や「謙遜」といった聖書の精神を忘れ、自分たちでこしらえた「口伝律法」の遵守に重きを置く彼らを「本末転倒」と、イエスから痛烈に批判された。「パリサイ派」「ファリサイ人」とも。
 K
K
この「パウロ」は、大祭司に諸会堂宛の手紙を書いてもらう事までして、ダマスコにいたクリスチャンたちを「エルサレム」へ強制連行しようとしていました。
その後、彼は擁護(ようご)するどころか、積極的に、自ら率先して「イエスの教え」を述べ伝えはじめています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
 K
K
また、パウロ自身、かつて自分がクリスチャンたちを迫害する側にいたことを「ガラテヤ人への手紙」の中で記しています。
このような彼の変化を説明するのも、彼が「復活したイエス」の声を実際に耳にし、その命令に聞き従ったとするのが、最も筋の通った説明と言えるのです。
全ては、弟子たちによる「イエス復活の証言」を信じるか否かにかかっている

中心的な11人の弟子(使徒)たちの内、10人までもが「イエスの死と復活」を証言したことによって殉教しています。
もし、”復活したイエスを目撃したという証言” がウソだとしたら、使徒たちは「ウソの目撃証言」のために死んだことになります。
人はふつう、ウソのために「自分の命」を投げ出すことはできないと思います。
先ほども言ったように、聖書によればイエスの死後、弟子たちは初め、自分たちも同じように捕らえられることを恐れ、戸に鍵を掛け、息を潜めるようにして過ごしていたのです。
しかもその記述から、弟子たちの大半(あるいは全員)が「イエスの復活」など信じていなかったことが読み取れます。
そのことはまた、安息日が過ぎたあと、彼に従っていた女性たちが「香油」をわざわざ購入し、それを塗るため、墓へと赴いている事実からも伺えます(マルコ16:1)。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
復活するというイエスの言葉を信じていたならば「香油」を用意することも、塗りに行くこともなかったでしょう。
また「マグダラのマリア」は、墓が空であるのを知って、遺体が誰かに持ち去られてしまったと思い、墓の外で泣いています(ヨハネ20:1~2、11~13)。
また、復活したイエスを目の当たりにした弟子たちが「幽霊」だと思って恐れおののいている描写もあります(ルカ24:37)。
”そんな弟子たちが、ある日を境に、命を投げ出してまで証言し始めた事実” を説明するには、彼らが「復活したイエスの姿」を実際、目の当たりにしたとする以上に説得力のある解答を、私たちは見出だせないのです。
圧力の単位の由来ともなっている優れた「物理学者」「数学者」そして「敬虔なクリスチャン」でもあり、かつて、フランス紙幣の肖像画にもなっていたパスカルの以下の言葉に、私は強く同意いたします。
私は、その証言の為に己の首を差し出す事を辞さぬ証人を喜んで信用する。
~ブレーズ・パスカル~
人が考えうる死の中でも最悪で、恥辱にまみれた死が十字架刑です。
この十字架の死に苦しんだ男を礼拝する宗教が社会に広がったという事実をどのように説明しますか。
もちろん、クリスチャンであれば、それはイエスが復活したからだと言うでしょう。
イエスの復活を信じない人々は、何か他の理由を考えようとするでしょう。
しかしイエスがよみがえったという説明以外は、どれも説得力に欠けています。
~エドウィン・M・ヤマウチ博士~
『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
イエスの復活が真実なら、何がどうなるというのか?
聖書になじみがない方からすれば……、
「で? イエスが復活したから何なの?」
と思われるかもしれません。
「2000年ほど前に復活したイエス」と「現代の私たち」の間には、何の関係もないように思えるからです。
ところがこれが、大アリなのです。
 K
K「イエスの復活」が事実なら、彼が聖書にて預言されていた「メシア」だということになる。
⏬
聖書の預言どおり「メシア」が現れ、殺され、復活したのならば「神の存在」も「聖書の言葉」も、真実だったということになる。
⏬
聖書によれば、神が送った「メシア」を通して神とつながっている者は、全員、同じように復活するのだという。
⏬
逆に、神とのつながりを取り戻さなかった人たちは、肉体を失った後、”神から完全に切り離された領域”で過ごす事になるのだという。
⏬
つまり、神が備えた「闇からの脱出口」である「イエス」を受け入れるかどうかによって、霊的な状態になった時の「永遠とも言える運命」が左右されることになる。
 眠れる羊くん
眠れる羊くんこのように、クリスチャンたちの信頼(信仰)が「イエスの復活」1点にかかっているように、私たち全員の「運命」も、”彼を受け入れるかどうかの1点” にかかっているのです。
正直なところ、イエスの復活が崩れれば、クリスチャンたちの信じていることは水泡に帰します。
イエスが復活しなかったとすれば、彼は「メシア」ではなかったことになり、”カリスマ性を持った、いち倫理的教師の1人” に過ぎなかったことになるからです。
逆に「イエスの復活」が真実であった場合、なかなか信じがたいことではありますが、私たちの復活も真実となるわけです。
無神論者
彼らは、いかなる理由から蘇(よみがえ)りが不可能だというのか。どちらがより難しいというのか、生まれることと蘇ることと、かつてなかったものが存在することとかつてあったものがまだ存在することと。
生を享けることは、生に立ち戻ることより難しいのではないか。
習慣のせいで一方は容易に思われ、習慣が欠けているせいでもう一方は不可能だということになる。なんと浅はかなものの考え方。
『パンセ(中)』 パスカル 著 塩川徹也 訳 岩波文庫
最も偉大な、最も優れた人々、すなわち、ダンテ、タウラー、アッシジのフランチェスコ、幾人かの使徒、いや、キリストその人も、その臨終の時に、――こころよい気分を味わいはしなかった。
したがって、太陽は輝きながら没しようと、雲に隠れて沈もうと、どちらでもよいのだ。いずれにしても、太陽は輝かしくまた昇ってくるのである。
『幸福論(第二部)』 ヒルティ著 草間平作 訳 岩波文庫
もし死後に再び目覚めることはないと仮定しても、現世において再生を信じた者が、その思い違いによって困るということはない。
彼らはその幻滅を意識することもなく、ただ一般の人間と運命を共にして滅びてゆくだけである。
ところで、もし逆に復活が実際あるとすれば、それを信じなかった人にとって、それは楽しいことであるはずがない。
まったく実利的にいえば、およそ信仰の利益は次の点にある。
すなわち、信仰を抱いている人は、万一その信仰が誤っていても、信仰を持たない人よりも現世でも死後でも不利にはならないし、またその信仰が正しい場合には、いっそう利益を受けることになる。
『幸福論(第二部)』 ヒルティ著 草間平作 訳 岩波文庫
まとめ
- 「復活」に対する信念は、イエスの死後、数年以内には構築されていたと考えられ、後世に付加された「伝説」の類ではない。
- イエスの「遺体消失」は、彼を否定する側も認めていることであり、番兵たちが居眠りする中、弟子たちが盗んだのだとするにはムリがある。
- 復活が「でっち上げ」なら、最初の発見者は、法的に証言者として認められていない「女性たち」でなく、ペテロやヨハネなどの「男性」にしたはず。
- イエスの復活を信じず、迫害を恐れ、身を隠していた弟子たちが「ある日」を境に、突然、証言しはじめたことを論理的に説明するには、復活したイエスを本当に見たとする以外ない。
- イエスを信じていなかった者たちが、彼の死後、態度を激変させている事実を理解するには、イエスの復活が事実であったとするのが最も合理的。
- イエスの復活が崩れれば、クリスチャンたちの信じていることは水泡に帰す。逆に「イエスの復活」が真実であった場合、私たちの復活も真実となる。
いかがだったでしょうか?
今回は「イエスの復活が信じるに足る根拠」について見てみました。
クリスチャンたちが「盲目的」にではなく、しっかりとした「根拠」にもとづいて、イエスを信じているのだということが、すこしでも伝われば幸いです。
終わりに、ストロベル氏の著書から、2人の人物の言葉をご紹介したいと思います。
長い記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
エリザベス女王から士爵の称号を2度授与されている元弁護士兼外交官のリオネル・ラックフー卿は、最も成功した弁護士として、ギネスブックにもその名を記されている。
その彼がイエスの復活について数年にわたって調査を行った結果、以下のように結論づけている。
「イエス・キリスト復活の証拠が圧倒的なものであることは明白で、疑念の余地が一切ないと信じさせるだけの力を持つ」『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
「神がイエスを死から復活させたという仮説は十分ありうることです。証拠を並べてみますと、それこそが、最も自然な理由であることがわかります。
イエスが奇蹟によるのではなく、自然に生き返ったということこそありえませんよ。それは絶対におかしいと私も思います。
――この仮説を信じるのに必要なのは、神が存在するという仮説を認めることだけです。
そして、この事実を認めるに必要なだけの理由もたくさんあると思います」
~クレイグ・L・ブロンバーグ博士~
『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
 眠れる羊くん
眠れる羊くん『イェシュア(イエス)が十字架上で死んだことにどんな意味があるのか?』へのリンクは下だよ。
一人の男が地下牢にいる。彼は自分の判決が下されたかどうか知らず、それを知るのにもはや一時間の猶予しかない。しかし下されたと知れば、それだけの時間で判決を取り消させるのに十分だ。彼がこの時間を使って、判決が下されたかどうかを調べるかわりに[…]
 K
Kこれまでの「真理探究の記事 一覧」のページに行けるよ♪