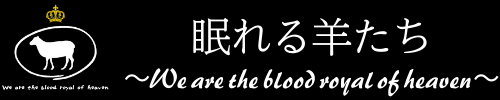K
K~ 聖書は信じるに値するか? No.22 ~
「十字架刑の実態」&
「”仮死状態であった説”の医学的見地」
について、お伝えしています。
「十字架刑」についてだけ知りたい方は……、
【前半(目次の1&2)】だけ読めば良いようになっています。
「もう少し踏み込んで知りたい」という方は……、
【後半(目次の3&4)】も、合わせて読んでみてください!
おそらく、ほとんどの方が「絵画」などをとおして、メシアが十字架に磔(はりつけ)にされている姿を見たことがあるのではないかと思います。
一方で、この「十字架刑」が、実際にどれほど残酷で屈辱的な「処刑法」であるかをご存知の方は、それほど多くはないかもしれません。
「十字架刑」は、罪人を意図的に長時間苦しめるべく考案されたローマの極刑です。
ではさっそく「十字架刑」について、詳しく見てみましょう。
【神の御業の丘陵 ― kami no miwaza no kyuuryou ―】
こうして上り坂を一歩一歩踏みしめていると、群衆の罵声が飛び交う中、刑場へと向かう彼の姿が目に浮かぶかのようです。
耳の奥では、かの音楽の父による「マタイ受難曲」がよみがえり、心を暗く染めます。
しかし私たちは、丘の頂上で、2000年ほど前に行われた「あの出来事」が何であったのかを検証しなければなりません。
それが現代の私たちと、いったい何の関わりがあるのかを知るために……。

※栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
十字架刑の前に行われた「鞭打ちの刑」の凄惨さ

 K
K医学博士、哲学博士。フロリダ、マイアミ大学にて医学博士号を取得。イギリス、ブリストル大学にてエンジニアリング博士号を取得。カリフォルニア大学での教授経験を持つ。
 眠れる羊くん
眠れる羊くんメテレル博士によれば「血汗症」が起きると皮膚が大変脆弱*になることから、ローマの「鞭打ち」を受ける前に、イェシュアの皮膚はすでにとても弱くなっていたと考えられるそうです。
* 脆弱(ぜいじゃく)…… もろくて弱いこと。
彼らの使う鞭(むち)は「フラグラム」と呼ばれ、鉄の玉が入った編み込み式の革紐であり、これで打たれると、中に入った鉄によって強度の「打撲傷*」と「挫傷**」が引き起こされます。
* 打撲傷(だぼくしょう)…… 物に打ちつけ、または打たれて生じた傷。
** 挫傷(ざしょう)…… 皮膚表面には損傷を生じないで、皮下組織、あるいは深部の軟組織を損傷すること。
【出典:広辞苑 第六版】
また、鞭には動物などの「鋭利な骨」も付けられており、この骨が深刻な「裂傷」の原因となったそうです。
鞭打つ回数は通常39回ですが、刑を担当する兵士の気分次第で、それ以上打たれることも珍しいことではなかったと言います。
しかも、鞭打たれる箇所は「背中」だけでなく……、
- 肩
- 腰
- 足
と、全身を打たれました。
このような鞭で打たれれば当然、皮膚は裂け、身体はボロボロの状態となり「脊椎(せきつい)」がむき出しになることもあったそうです。
この「鞭打ち刑」を研究した医者によれば、鞭打ちが続くと、裂傷が皮膚の下にある「骨格筋」にまで達し、裂傷によって紐状*となった筋肉が震えるのだと言います。
* 紐状(ちゅうじょう)…… ひものように細長いかたち。
【出典:精選版 日本国語大辞典】
3世紀の歴史家である「エウセビオス」は、ローマの鞭打ちについて……、
「鞭打たれた者の血管がむき出しになり、筋肉、腱、内臓までが飛び出しかねない」と記しています。
メテレル博士によれば、鞭打ちで命を落とさなかったとしても「とてつもない痛み」と「血液量減少性ショック」に苦しんだことは確かだろうと言います。
「血液量減少性ショック」とは、大量の血液が急激に失われることことによって起こるショック状態のことであり、主に、以下のような4つの症状を呈するものです。
- 大量の血液が失われているにも関わらず、それでも心臓は、少ない血液を必死で全身に送ろうとするため、心臓の鼓動が速くなる。
- 血圧が下がることによって、気を失う。
- 残された血液量を維持するため、腎臓が「排尿作用」を停止する。
- 血液が大量に失われることによって、喉が異常に渇く。
②……「福音書」には記録されていませんが、伝承では「ゴルゴタの丘*」へ向かう途中、十字架を背負ったイェシュアは3度、倒れてしまったことが言い伝えられています。
また、イェシュアの状態を見かねたローマ兵が、傍らにいた「キレネ人シモン」という男に、彼の十字架を担ぐよう命令するシーンもあります。
* 「されこうべ = 頭骨」の意味。「カルバリの丘」とも言う。

もはや十字架を背負える状態ではないと判断したローマ兵は、シモンに十字架をかつがせた
 K
K
④…… また、十字架上のイェシュアが「喉の渇き」を訴えている描写があることからも、イェシュアが十字架につけられる以前に、すでにこのショック状態にあったことが推測できます。
「医療のプロフェッショナル」であるメテレル博士は、以下のように明言しています。
「鞭打ちによる深刻な影響から、十字架につけられる前のイエスがすでに重体であったことは間違いありません」
十字架刑前の「精神的な屈辱」
この「鞭打ち刑」だけでも、私たちには到底、耐えきれそうにありませんが、彼が受けた苦しみは「肉体的」なものだけではありませんでした。
以下は、鞭打たれ「ボロぞうきん」のような状態になったイェシュアに対する、ローマ兵たちの様子です。
兵士たちは、官邸、すなわち総督官邸の中に、イエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。
そして、イエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、「ユダヤ人の王、万歳」と言って敬礼し始めた。
また何度も、葦の棒で頭をたたき、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。
マルコによる福音書 15:16~19(新共同訳)

茨(いばら)の冠
彼らにとって「罪人の処刑」とは、”退屈な日常をまぎらわす、ひまつぶしの余興” 的なものだったようです。
無実であった彼は、このように「鞭打ち」に加え「精神的な恥辱」をも受けたわけですが、
ただ、これはまだ「序章」に過ぎず、十字架刑の凄惨さは、実はここからが本番なのです。
彼は「十字架刑」で確実に死んだのか?

「同じことをすれば、お前たちもこうなるぞ」というような「見せしめ」の要素を持った死刑法であり、絶命までの時間を故意に引き伸ばす工夫がなされた非常に残虐な処刑法として、当時、最も重い刑罰であった。
出典:Wikipedia
あまりの残虐さに「ローマの市民権」を持つ者に対して、この十字架刑が執行されることは、ほとんどなく(ただし、皆無ではなかったらしい)、
主に重罪を犯した「奴隷」や「ローマ人以外の人々」が対象でした。
聖書によれば「メシア(キリスト)」だと考えられているイェシュアは、この「十字架刑」の後に、復活したとされています。
そして実はこの「復活」こそ、クリスチャンたちが信じていることの「土台」の部分を形成するものであり、仮にこれが崩れた場合、世界に数十億といるクリスチャンたちの信仰は「土台」を失った建物のように、崩壊すると言って差し支えありません。
 K
K
この「復活」の真偽を確かめる前に、当然ながら、まずは「彼が本当に死んだのか?」という点について確認する必要があるかと思います。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
このように「聖書は信じるに値するのか?」ということを判断するにあたって、”イェシュアが確実に死んだかどうか” という点は、実は、とても重要なポイントとなるのです。
もしかしたら、イェシュアが復活したことについて、懐疑的な多くの人々は、
「彼は、仮死状態になっただけで、あとで息を吹き返したんじゃないの?」
と思われるかもしれません。
これから私たちは、メテレル博士と共に「十字架刑」について、詳しく見ていくわけですが、
十字架刑がどのようなものか、具体的に知ったあとでも、この「仮死状態説」を、あなたがまだ信じていられるかどうか、ぜひ試してみてください。
 K
K【十字架刑の過程】ピラトの官邸~刑場での釘打ちまで
「鞭打ち」のあと、すでに重傷を負っていたイェシュアは、十字架の「横木」の部分だけ背負わされ、刑場である「ゴルゴタの丘」へと歩かされます。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん現在、この「ピラトの官邸」~「ゴルゴタの丘」までの、およそ1kmほどの道のりは、
「ヴィア・ドロローサ(苦難の道)」と呼ばれ、クリスチャンたちの巡礼地となっています。
刑場へ着くと、衣服を脱がされ裸にされた受刑者は、横に寝かされ、背負っていた「横木」に釘で固定するため、両手を横に広げさせられます。
絵画などでは「腰布」的なものをまとっている姿で描かれることが多いですが、さきほど説明したように、十字架刑は「見せしめ」のための刑でもあることから、下着もすべてはぎ取られた状態で行われました。
想像してみてください。
- 「いい気味だ」とせせら笑う指導者たち
- 残虐行為を楽しむローマ兵たち
- 野次馬根性むき出しの大衆
- 自分のことを訴えた者たち
- 母親(マリア)
- 友人・知人
- 弟子たち
- 親族
これらすべての人々の前で、丸裸にされ、十字架につけられることが、どれほどの屈辱かを。
しかも、仮に聖書の記述が真実であるならば、彼は、上記の人々をも含めた全ての人たちに「救いの道」を備えるため、自らすすんで、このような屈辱を受けたというのです。
「福音書」には、嫉妬からイェシュアのことを「十字架刑」へと追い込んだ宗教指導者たちなどが、磔(はりつけ)にされた彼に取った態度が記録されています。
そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスをののしって、言った。
「神殿を打ち倒し、三日で建てる者、神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りて来い。」
同じように、祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒に、イエスを侮辱して言った。
「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。
神に頼っているが、神の御心ならば、今すぐ救ってもらえ。『わたしは神の子だ』と言っていたのだから。」
マタイによる福音書 27:39~43(新共同訳)
民衆は立って見つめていた。議員たちも、あざ笑って言った。
「他人を救ったのだ。もし神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい。」
兵士たちもイエスに近寄り、酸いぶどう酒を突きつけながら侮辱して、言った。
「お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。」
ルカによる福音書 23:35~37(新共同訳)
 K
K
この後、13~18cmほどの長さの「大釘」を手に打ち込まれるのですが、こちらも絵画等では「手のひら」に打ち込まれている描写がよくなされています。

十字架刑で使われた「大釘」のイメージ
また、メテレル博士によれば、当時の言葉では「手首」も「手」に含まれていたそうです。
この大釘が打たれる位置には、手を通っている中で最も太い「正中神経」があり、釘が打ち込まれるたびにこの神経が破壊され、最終的に「手」と「腕」は麻痺してしまうと言います。
それがどのような痛みであるかを、博士は次のように説明しています。
「こう説名すればいいでしょうか。ひじを何かにぶつけて、尺骨を打ったときに感じる痛み、わかりますか。
あれは、尺骨神経と呼ばれる神経のあるところです。うっかりここを何かにぶつけると、かなりの痛みを感じます。
いいですか。ペンチでもってその神経をひねりつぶしている様子を想像してみていてください。――イエスが経験した痛みは、そんな感じです」
『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
「到底耐えられる種類の痛みではありません。実際、このときの痛みを表現する言葉がなかったために、新しい言葉が創られています。
耐えがたいという意味の Excruciating という言葉なのですが、『十字架から』というのがその逐語的な意味なのです。
考えてみてください。十字架刑によるとてつもない痛みを表現する言葉がなかったために、新しい言葉を創り出さなければならなかったのですよ。そのくらいの激しい痛みなのです――」
出典:同上
想像を絶する「十字架刑」の苦しみ
その後、受刑者は十字に組まれた木の上に吊り上げられ、足にも「大釘」が打たれます。足は両足を重ねて、1本の釘が打たれました。
 K
K
足に「大釘」を打ち込まれるイェシュア
 眠れる羊くん
眠れる羊くんちなみに、足元には「足台」が、付けられていました。
「十字架」が固定されると自重が両腕にかかることから、受刑者の腕は横に15cmほど伸び、両肩は脱臼してしまうのだそうです(詩篇22の成就)。
わたしは水となって注ぎ出され
骨はことごとくはずれ
心は胸の中で蝋のように溶ける。
詩篇 22:15(新共同訳)
博士によれば、吊るされることで「呼吸筋」と「横隔膜」は緊張状態となり、息を吸い込んた状態で胸部が固定されるような形となると言います。
息を吐き出すには、この緊張状態を一時的に緩和するため、足を突っ張らなければなりません。
息を吐き出せば、つかの間、身体の力を抜くことができますが、突っ張っていた足の力を抜けば、自然に息を吸い込む形となります。
受刑者はこのように、呼吸をするため、体を持ち上げる動作をくり返すこととなるわけですが、言うまでもなく磔に使用される木材は、きれいにヤスリがけがなされたような代物ではありません。
それゆえ呼吸をするたびに、鞭打ちで皮膚の裂けた背中は、ざらざらの縦木にこすりつけられるような形となるわけです。
その痛みだけでも、相当な苦痛であろうことは想像に難くないでしょう。
 K
K K
K
十字架刑の苦痛は、我々が想像する以上のものであり、到底、耐えきれるものではない
そして、血液中の「二酸化炭素」が分解され炭酸となり、血中の酸度が増加する「呼吸性アシドーシス」という症状が起き、心拍異常が発生するそうです。
次第に「全身の筋肉」が疲弊し、呼吸のために身体を持ち上げることもできなくなり、やがて絶命へと至ります。
意外に思えるかも知れませんが、いま見てきたように、十字架刑による最終的な死因は「窒息死」ということになるのです。
「仮死状態説」は、医学的に見てあり得ない
メテレル博士は医学的な見地から、以下のような見解を示しています。
「――すでに血液量減少性ショック状態にあったイエスの心拍数は、死を迎える前にすでに異常に上がっていて心機能不全を起こしていたと思われます。
この結果、心臓の周りには心嚢水(しんのうすい)という液体が、そして肺の周りには胸水(きょうすい)という液体が貯留します」
『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
「イエスが死んだかどうかを確認するために、ローマ兵が彼の右脇腹を槍で突いています。
はっきりとしたことはわかっていませんが、説明を読むとおそらくイエスの右脇腹、肋骨の間を突いたと思われます。槍は右肺から心臓に到達します。
そして槍を引き抜くときに水のように見える心嚢水と胸水とが体外に排出され、その後、大量の血がやはり体外に排出されます。これはちょうど、ヨハネの福音書に書かれている説明と一致しています」
『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
確かに「ヨハネによる福音書」によれば、イェシュアの脇腹から「血」と「水」が流れ出た、ということが記されています。
しばしば、十字架上のイェシュアは単に「仮死状態」にあっただけであって「復活」ではなく「蘇生」したにすぎないのだと言われますが、
医学の専門家であるメテレル博士は、この時点でイェシュアが死亡していたことは、絶対に間違いないことであると断言しています。
ちなみに、彼の脇腹を突き刺した槍は「聖槍(せいそう)」と呼ばれ、聖遺物の1つとされています。
 K
K- 【余談】伝説の槍のその後……。
- ”ロンギヌスの槍の所有者は世界を制する”との伝承があるこの槍は「歴代のローマ皇帝」や「ハプスブルク家」「アドルフ・ヒトラー」などの手を、転々としてきた。
特にヒトラーは、この「聖槍」に異常なまでに魅了されたらしく、1938年、ドイツがオーストリアを併合すると「ハプスブルク家」の財宝と共に、この槍も手にした。
「ナチス」による彼の野望は、この聖槍から受けた「強烈な霊感」がきっかけだとも言われる。
1945年、アメリカ軍によって奪還された「ロンギヌスの槍」は、現在、ウィーンの王宮博物館に展示されている。
「ロンギヌスの槍」とされているものは、この他にも、ローマの「サン・ピエトロ大聖堂」にあるものなど数本存在しており、どれが本物なのかは不明。
また当時、囚人や受刑者に逃げられた場合、処刑を担当する兵士自身が「死刑」に処せられることになっていたので、ローマ兵はイェシュアが確実に死んだかどうかを念入りに調べたはずであることも、博士は指摘しています。
その点から見ても、イェシュアが実は生きていたとする考えには、相当無理があると言わざるを得ないわけです。
「歴史的、医学的証拠は、ローマ兵に脇腹を刺される前にイエスが死亡していたことをはっきりと証明している。
(中略)同時に、イエスが十字架の上で死ななかったという想定をもとにした事象の解釈は、現代の医学知識と合致しない」
ウィリアム・D・エドワーズ博士 1986年「米国医師会誌」に発表した論文より
『ナザレのイエスは神の子か?』
リー・ストロベル著 いのちのことば社
仮に百歩ゆずって、彼が死んでいなかったのだとしても……、
- 全身の皮膚は裂け
- 大量の血液を失い
- 手足を釘に貫かれ
- 両腕の神経は破壊され麻痺し
- 両肩は脱臼し
- 脇腹を槍で突き刺された状態
の彼が三日後に蘇生し、自ら起き上がって全身に巻かれていた「亜麻布」を取り去り、墓の入口を塞いでいた「巨大な石」をひとりで転がし、
墓の前で「見張り」をしていた者たちの目を運良くかいくぐり、何ごともなかったかのような健康体で、しかも自らの足でかなりの距離を歩いて弟子たちの前に現れ、
再び弟子たちに教えはじめることなど、果たして可能なことでしょうか?
何よりも、もし彼が「仮死状態」から蘇生しただけであったとしたら、
その後、残った11人の使徒たちの内10人までもが、死を覚悟しつつ、イェシュアの復活を証言して殉教*している事実をどう理解したら良いのでしょう?
* 自分が信じていることのために、命を落とすこと。
彼らおよび、その他の多くの弟子たちが、命を賭してまで証言し続けたのは、
実際に復活したイェシュアの姿をその目で見、やがて自分たちもその復活の身体に与(あずか)ることを確信したからだと考えるのが、最も合理的で筋の通った見方なのです。
【合わせて読みたい】
『理屈っぽく、宗教嫌いの私が、それでも聖書と神を信じる4つの理由』

「福音書」によれば、母マリアも十字架刑場にいたことが記録されている
 眠れる羊くん
眠れる羊くんもう少し踏み込んで知りたい方以外は「まとめ」へジャンプ!
十字架刑による「預言」の成就

 K
K
イェシュアと共に十字架につけられた2人の受刑者は、日付が変わる前に、ローマ兵によって足の骨を折られています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
これは、翌日が「特別な安息日」であったことから、翌日まで十字架上に「死体」が残っているのを、ユダヤ教の指導者たちが避けようとしたためです。
足の骨を折ってしまえば、さきほど説明したような、呼吸のために足を突っ張って身体を持ち上げる動作ができなくなるため、その死が早まるというわけです。
一方でイェシュアは、すでに絶命していたことから、足の骨は折られずに、その死の確認のために脇腹を突かれました。
これによって、「その骨は一つも砕かれない」という預言が成就したと考えられています。
一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない。また、その骨を折ってはならない。
出エジプト記 12:46(新共同訳)
翌朝まで少しも残してはならない。いけにえの骨を折ってはならない。すべては過越祭の掟に従って行わねばならない。
民数記 9:12(新共同訳)
上記の2つの聖句は「ユダヤの3大祭り」の1つである「過ぎ越しの祭」に関する規定を述べたものです。
 K
Kこの祭りでは「傷の無い子羊」が犠牲として捧げられるのですが、これは、私たちの「罪」を帳消しにするため、自らの命を捧げた「罪の無いメシア(キリスト)」の予型*だとされています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くんある事柄を理解させるために、前もって似たような「ひな形」を示しておくこと。「本体」に対する「影」のようなもの。
このように、モーセの律法にて預言的に規定されていた通り「犠牲の子羊」=「メシア」の骨は、折られなかったというわけです。
主に従う人には災いが重なるが
主はそのすべてから救い出し
骨の一本も損なわれることのないように
彼を守ってくださる。
詩篇 34:20~21(新共同訳)
十字架刑による彼の死は「非常に不自然なもの」だった!?

「福音書」によれば、イェシュアは午前9時ごろ、十字架につけられ、午後の3時ごろに息を引き取っています。
 K
K
まずは、以下の聖句をご覧ください。
アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。
(略)ピラトは、イエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、既に死んだかどうかを尋ねた。
マルコによる福音書 15:43~44(新共同訳)
「ピラト」とは当時、ユダヤの統治を任されていた「ローマ帝国の総督」です。
「ユダヤ教の指導者たち」や「群衆」の圧力に屈して、イェシュアに「十字架刑」の判決を下した人物でもあります。
このピラトが、イェシュアの死を聞いて、驚いているわけです。
なぜなら「十字架刑」は見せしめのため、意図的に「苦しみ」を長引かせるための処刑法であり、2~3日後に息を引き取ることも珍しくなかったからです。
それに対し、イェシュアは、わずか6時間ほどで息を引き取ってしまったわけですから、ピラトが不思議に思い、わざわざ部下に確認したのもうなずけます。
それを裏付けることを、生前、イェシュア自身が口にしています。
わたしは命を、再び受けるために、捨てる。それゆえ、父はわたしを愛してくださる。
だれもわたしから命を奪い取ることはできない。わたしは自分でそれを捨てる。
ヨハネによる福音書 10:17~18(新共同訳)
つまり、彼は自らの意思で、その生命を神に捧げたということです。
ちなみに先ほど聖句にあったように「アリマタヤのヨセフ」という身分の高い人物が、彼の遺体を引き取ることを願い出たのですが、
「ハーベスト・タイム・ミニストリーズ」の中川健一氏によると、十字架刑後の遺体を、手厚く墓に葬ることは「恩赦」に当たるものだそうです。
そして、その「恩赦」に当たる埋葬を「ローマの総督ピラト」が許可したのは、ユダヤ人に対する「かすかな抵抗」を試みたのではないか、と指摘しています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
息を引き取ったイェシュアを、丁重に十字架から下ろす、ヨセフや女性たち
ピラトは「十字架刑(磔刑――たっけい)」の判決を下した張本人であることから「冷血漢」として見られがちですが、
イェシュアの「十字架刑」を回避させようとしたり、遺体の引き取りを許可したりと、どちらかと言えば、イェシュアに対しては「同情的」な態度を示した人物でもありました。
それは、もしかしたら……、
- イェシュアと交わした「会話」
- 彼の「理知的な雰囲気」
- 彼の「不自然な死」
などから、この無実の受刑者に対し、何らかの「真実性」を感じ取っていたのかもしれません。
まとめ
- ローマの「鞭打ち」は凄惨で、「皮膚」は裂け「筋肉」や「骨」はむき出しになり、時には「脊椎」がむき出しになることもあった。
- 鞭打ちによって、イェシュアは「血液量減少性ショック」の状態にあったと考えられ、十字架刑前に、すでに重体であったことは間違いない。
- 十字架刑は「見せしめ」であり、絶命までの時間を故意に引き伸ばす工夫がなされた残虐な処刑法。
- 釘は「手の平」でなく「手首」に打ち込まれた。この位置には「正中神経」があり、打ち込まれる度にこの神経が破壊される。これは、ひじにある「尺骨神経」をペンチでひねりつぶすような痛み。
- 吊るされると「横隔膜」等が固定された状態となり、呼吸困難となる。受刑者は呼吸のため「鞭」で傷だらけの背中を十字架の荒木にこすりつけながら身を持ち上げる動作を、長ければ2~3日も繰り返す。
- 十字架刑の最終的な死因は「窒息死」。
- 医学博士のメテレル氏によれば、「仮死状態説」は、医学的な見地からすれば「ほぼ不可能」に近い。
いかがだったでしょうか?
今回は「十字架刑の実際」について、見てみました。
暗い気持ちになってしまうような内容ではありましたが、
「イエスって、気絶してただけで本当は、まだ生きてたんじゃないの?」という考えが、かなりムリのあるものだということが、お分かりいただけたのではないでしょうか?
こうして今、私たちは、彼の「復活」の真偽を考察する地点へと、ようやくたどり着きました。
次回は「イェシュア(イエス・キリスト)の復活は信じるに値するか?」という点に的をしぼって、旅に出ることにしましょう。
長い記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん『イェシュア(イエス)の復活は真実か? 聖書が提示する5つの根拠』へのリンクは下……💤
復活のことを切り離して考えれば――十字架で死んで、ただ葬られただけの「神の子」など、我々に何の役に立つであろうか。そういうことは誰も信じないであろう。逆に復活という事実からキリストを神の子と結論することは、きわめて論理的に一貫した[…]
 K
Kこれまでの「真理探究の記事 一覧」のページに行けるよ♪