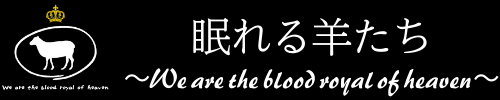このブログでは…… 、
「宗教とは距離を置きつつ、聖書を人生の土台として生きる」
ことを提案しています。
詳しくは「目的のページ」をご覧ください。
「自分の力だけで世の中を渡る事が、いかに無謀なことか」
「辛い状況に対する聖書的、および一般的『対処法』」
について、お伝えしています。
まずは、単刀直入にあなたに伺いたいと思います。
「あなたは今、自分の力だけで生きていませんか?」
「社会に出たら、自分の力で生きていくのは当たり前だろ!」
と、あなたは思われるかもしれません。
しかし、違うのです。
少なくとも、これから私がご紹介しようとしている「聖書」という、古くて何とも不思議な書物の中では、そのような生き方は、最も大きな「罠」だとしています。
「聖書」と聞いて、あなたは「宗教」を思い浮かべたかもしれませんが、これは宗教の話ではありません。
私自身、何らの宗教団体にも属していませんし、いわゆる「教会」と呼ばれている「建物」に通ってすらいません。ただ、聖書を信じているのみです。
あなたは、神など信じていないかもしれませんが、
”神から離れて社会で生きていく”ということは、”フラッとコンビニにでも行くような軽装で、富士登頂に挑むようなもの”と言えます。
もし、あなたが人生に行き詰まり、どうして良いのか分からない状態にあるなら
「これまであなたが見向きもしなかった方へ、今こそ目を向けるべき時だ」と、私は心からあなたにオススメしたいと思います。


※栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
助けて、辛い | 仕事のストレスに晒されたあなたの驚くべき無防備さ

冒頭でもお話したように「神から離れて社会で生きていく」ということは、「フラッとコンビニにでも行くような軽装で、富士登頂に挑むようなもの」なのです。
言い換えれば、”不可能ではないが、ちゃんとした装備をそろえておいた方が良いに決まっている” ということです。
考えてみてください。
「裸足にサンダル履き」よりは、
「登山靴」の方が足を痛めにくいですし、
夏と言えども頂上付近は寒いですから、
「Tシャツ + ハーフパンツ」よりも
「速乾性のシャツ + 長ズボン」を着て行き、
「重ね着用の防寒着」も用意しておいた方が良いはずです。
また、山の天候は変わりやすいですから、
「レインウェア」も備えておくべきでしょう。
その他、
- ザック
- 帽子
- 手袋
- 厚手の靴下
- サングラス
- 飲料
また、場合によっては「携帯用の酸素缶」などなど…… 、
「登山に行くなら絶対あった方が良いよね」というものがあるはずです。
逆に言えば、もし、あなたが前記のような軽装で富士登山に行こうとしている人を見たら、いささか無謀だと思うのではなでしょうか?
しかし、ある面では、この登山の困難にも遥かに勝るとも言える「社会」に出ていく段になると、そのような「備え」のことなどスッポリと頭から抜け落ち、私たちは驚くほど軽装で社会に出て行ってしまうのです。
その原因は…… 、
- そのような「備え」について、学校や家庭で教わらないため。
- ある程度タフ、もしくは鈍感な人は、それで何とかやれてしまうため。
- そもそも何をどのように備えたら良いのか、分からないため。
などが考えられます。
助けて、辛い | 聖書の人生観で ”仕事のストレスに対する耐性” が高まる

さきほどの「喩え」を再び用いるならば、
”聖書の人生観を自分の内にインストールする” ということは、”登山用のさまざまな装備を整える” ようなものです。
そして、この書物は「人生」という名の山登りに必要な「装具」であると同時に、「地図」のような側面をも持ち合わせています。
 K
Kもちろん、世の中で生きていく以上、そのようなストレスを完全に無くしてしまうことはできませんが、
しかし、それらのストレスに対する「耐性」を高めることは可能なのです。
その力を私たちに与えてくれるものは…… 、
- 哲学書
- 自己啓発書
- スピリチュアル本
などの類ではありません。聖書こそが、その最たるものなのです。
そうでなければ、数千年もの間、数え切れないほどの理知的な人々の心を捕らえ続けてくることなど、できようはずもありません。
そして、神のもとへ立ち返り、聖書の人生観を自分の内にインストールして生きることは、何らかの宗教団体に属さずとも、できることなのです。
助けて、ストレスでキツイ | 仕事が辛い「9つの原因」と「アドバイス 」

 K
K《 目次:仕事が辛い9つの原因 》
- 「職場環境」や「労働環境」がストレスになっている。
- 人間関係がストレスになっている。
- 仕事量の多さがストレスになっている。
- 不向きな仕事がストレスになっている。
- 能力の無さによる自信喪失がストレスになっている。
- ハラスメントの横行がストレスになっている。
- 過大なプレッシャーがストレスになっている。
- 相談相手のいないことがストレスになっている。
- やりがいの無さがストレスになっている。
①【「職場環境」や「労働環境」がストレスになっている】
- 給料が不当に安過ぎる。
- サービス残業をさせられる。
- 休日出勤を強いられる。
- 福利厚生が不十分。
- 有給休暇が取得できない。
このような場合は「ブラック企業」の可能性もあるので、転職なども考慮すべきかもしれません。
人生には、全力で逃げるべき時があるものです。
また、
- 炎天下での作業。
- 冷蔵・冷凍庫内での作業。
- 著しく不衛生な環境での作業。
- 換気の不十分な環境での作業。
- 夜勤のある業務。
等々、肉体的に過酷な条件下で、健康を損ねる可能性がある場合などもあるかと思います。
このような場合、既に健康に異常を感じているのであれば「我慢」や「気力」でどうにかしようとせずに、すぐに異動を願うか、やはり転職を検討すべきでしょう。
私自身、関節リウマチという病で体中の関節が炎症を起こし、ひどい痛みで半年ほど働けなくなった経験があります。
ですから健康を損ね、働けなくなってしまう事態だけは、何が何でも避けなければなりません。
②【人間関係がストレスになっている】
- 苦手な上司がいる。
- 職場の人たちと上手く噛み合わない。
- 社内全体の人間関係がギスギスしている。
などなど、職場でのストレスの大半は「人間関係」に起因すると言えます。
ただ、どの職場にも大抵、気の合わない人はいるもの……。
そういった人とはムリに距離を縮めようとする必要はありません。
業務上、必要な場面以外では深く関わらず、あくまでも仕事と割り切って接するようにしましょう。
 K
K人から悪く言われるのは辛いものだ。しかし、トマス・ア・ケンピスが言っているように、人の悪口は「空しい名誉の魔の霧」から我々を守ってくれる。
そして、我々の心の奥を知りたもう神を、自分の証人として、審判者として求めるようにしむけるものだ。
こうして初めて、神は我々にとって欠くことのできないものとなり、我々と堅く結ばれるのである。
だから、多くの名誉を得ても損なわれない人間になるには、まずこのような屈辱をくぐり抜けることが、特に必要である。
『幸福論(第二部)』ヒルティ著 草間平作 訳 岩波文庫
③【仕事量の多さがストレスになっている】
どんなに優れた人であっても、こなせる業務量には限りがあります。
部下や同僚等、人に任せることのできる仕事は思い切って任せ、自分ひとりで何でもかんでもこなそうとしないことは、自分を守る上で、とても重要です。
④【不向きな仕事がストレスになっている】
営業職・技術職等、実際にやってみたところ「職務内容が自分に合わない」と感じることは往々にしてあるものです。
ただ、技術が身についてくると、それまで気づきもしなかった「面白み」が見いだせるようになる、ということもあるでしょう。
一方、「経営方針」や「社風」に馴染めないと言った場合は、なかなか自分の力でどうにかなる問題でもありませんので、転職や独立といった選択肢も考慮すべきかもしれません。
⑤【能力の無さによる自信喪失がストレスになっている】
「メモを取る癖をつける」「専門書などを読んで知識をつける」など、努力によってカバーできる点については、全力を注ぐべきことは言わずもがなです。
日本人の多くは学校を卒業して社会に出ると、パタリと勉強をやめてしまうものですが、ここで勉強を続けるかどうかによって、将来、大きな差が生まれることでしょう。
また、「全か無か思考」と「べき思考」をやめることも大切です。
◼「全か無か思考」……
わずかでもダメな点があると、その他の良い点もろとも否定してしまう、いわゆる「完璧主義」のこと。
◼「べき思考」……
「〇〇でなければならない」等、自らを檻に閉じ込め、柔軟な行動や発想を制限してしまう考え方。
⑥【ハラスメントの横行がストレスになっている】
ハラスメント(嫌がらせ)には、立場上の優位性を利用した「パワハラ」や、
性的な嫌がらせである「セクハラ」に加えて、
相手の人格を否定する・無視する・暴言を吐く等、立場の上下に関係なく、言葉や態度によって嫌がらせをする「モラハラ」などが有名です。
このような「ハラスメント」に対しては、勇気のいることではありますが、
- 録音しておく。
- 可能であれば、スマホ等で録画しておく。
などして証拠を押さえておくと、ハラスメントを行った人の、更に上の上司に見せることで、武器として利用できるかもしれません。
⑦【過大なプレッシャーがストレスになっている】
これは、営業職において課せられるノルマが高い場合や、重要なプロジェクトの責任者として、プレッシャーに押しつぶされそうになっている場合などです。
営業職には、向き不向きの要素も大きいかもしれませんが、「ビジネス書」や「心理学」関連の書籍を通して学びながら、やはり地道に経験値を積むしかないのではないかと思います。
「プロジェクトの責任者」や「管理職」の場合、
聖書の人生観を自分の土台とし、神と共に人生を歩んでいくことが、あなたのメンタルを守るための最上の道だと言えるでしょう。
⑧【相談相手のいないことがストレスになっている】
これは、神から離れて生きている人たちにとっては、切実な悩みでしょう。
しかし、私たちクリスチャンからすると、”周囲に相談相手がいないこと” は、
何の問題にもなりません。
なぜなら私たちは、本来、人ではなく神に頼って生きるように創られているからです。
 K
K⑨【やりがいの無さがストレスになっている】
このような方には「会社での仕事は生活のため」と割り切って、やりがいを感じられそうな「副業」をはじめてみることをオススメいたします。
「副業」でなくとも、何らかの「ボランティア活動」や「趣味仲間との集まり」みたいなものでも良いかもしれません。
「副業」のみで生活費を稼ぐのは、簡単なことではありませんから、
「生活のための仕事」と「やりがい(生きがい)のための仕事」
を両立し、両者を完全に分けて考えるようにするのです。
助けて… | 辛い仕事のストレスから逃げることは、甘えとは限らない

「上司に小ごと言われたからもう嫌だ」
「満員電車が面倒だからもう辞めたい」
などの場合は別として、
例えば…… 、
「上司のパワハラで、死にたく感じるほどに追い詰められている」
「長時間労働で、体調不良がずっと続いている」
などの場合は、今すぐにでも、そこから抜け出す準備をはじめるべきです。
さきほども言いましたが、人生には、全力で逃げるべき時というものがあるのです。
後者の場合、退職することは「甘え」などではありません。そんな時に、精神論を振り回している場合ではないのです。
戦争中、日本の若い技師が「レーダー」を発明し、上司に提案したところ、上司は、その画期的な発明の有用性に気づけないどころか、
「バカモノ! 我々は大和魂で戦うのだっ!」
と一蹴されたと言います。
「精神的な強さ」いわゆる「強気」というものは、もちろん大切です。しかし、時と場合によっては、その「精神論」が命取りになることもあり得るのです。
聖書にも、以下のような教訓が書かれています。
† 賢明な者は悪いことを予見すると身を隠す。
しかし、無知な者は通り過ぎてひどい目に合う。
箴言 27:12(旧約聖書)
心や体が限界を感じ、健康が損なわれようとしている時、そこから逃げ出そうとすることは「甘え」などではありません。
むしろそれは、自己の心身を守ろうとする「自然な反応」です。
私たちの国では、我慢を美徳とするような面がありますが、いつ如何なる時も、我慢することが必ず正しいとは限らないことを、忘れてはいけません。
助けて… | 仕事のストレスが辛い時の「対処法」

 K
K仕事のストレスが辛い時の「聖書的な対処法」【3選】
《 目次:聖書的な3つの対処法 》
①【悪に対して悪で報いない】
例えば、あなたが上司や同僚、取引先の人などから理不尽な扱いを受けた時、
それを恨みに思って、何らかの別な形で(相手には気づかれない形であっても)やり返そうなどと思ってはいけない、というのが聖書的な教えです。
聖書には、以下のような言葉があります。
†「彼が私にしたように、私も彼に対してしよう。
彼の行いに応じて、私もあの者に報いよう」とは、
あなたの言うべきことではない。
箴言 24:29(旧約聖書)
 K
Kつまり、自分で仕返しをする必要などないのです。それどころか、神の領分に私たちが手を出すことなど、してはならないのです。
聖書的に見た場合、仕返しをすることは、とても低レベルな反応の仕方なのです。
また、よく誤解されがちな聖書の言葉として、以下のようなものもあります。
† 悪人に手向かってはならない。
だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。
あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。
マタイによる福音書 5:39~40(新約聖書 新共同訳)
これは「何をされても、やられたい放題になれ」と言っているのではありません。身の危険を感じたなら、私たちは当然、逃げるべきです。
ここで言っているのは、先の教えと同様、「報いは神がしてくださるのだから、自分でやり返そうなどとはせず、神に信頼せよ」ということです。
ですから私たちは、人から理不尽な扱いを受けた際、相手と同じ低いレベルまで下がるようなことは、もうやめにしましょう。
②【”蒔いた種は必ず刈り取る” という法則を知る】
† ――悪事を成す者は、
自分が成したその悪事を受け取る事になるでしょう。
そこに依怙贔屓(えこひいき)はありません。
コロサイ人への手紙 3:25(新約聖書)
† 私はあなたがたに言います。
人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて、
裁きの日には責任を問われます。
あなたは自分の言葉によって義とされ、
また、自分の言葉によって罪ある者とされるからです。
マタイによる福音書 12:36~37(新約聖書)
 K
K「人は、自分が蒔いた種を刈り取ることになる」的な言葉を、多くの方は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
実は「引き寄せの法則」に代表されるような、いわゆる「成功哲学」の源流は、聖書にあります。
 眠れる羊くん
眠れる羊くんこれも「人間関係におけるストレス」に対処するための処世訓になりますが、
ぜひ私たちは、同僚がどんなズルをしようとも、上司に成果を横取りされようとも、心を乱さずに、泰然としている努力をしようではありませんか。
必ずその人は、自分が蒔いた「毒麦」の実りを、いつの日か刈り取るハメになるのですから。
それだけではありません。神は、あなたが失ったものを、何らかの形で、数倍にして返してくださいます。
このような真実の法則を知っているのといないのとでは、受けるダメージ(ストレス)が全く違ってくるものです。
カッとなったら負けです。
スピリチュアルな視点から見た場合、その瞬間、あなたは既に敵の術中にハマっていると言えます。
【参考】
『人生とはスピリチュアルな戦いである。究極的には誰も助けてはくれない』
もちろん簡単ではありませんが、あくまでもクールに、泰然として「偽り」や「不正」といった悪を眺めるクセを付けましょう。
③【自分の力が及ばない事に関しては神に委ねる】
広く知られた祈りとして、以下のようなものがあります。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん神よ、変えることのできないことを平静に受け入れる恵みを、
変えるべきことを変える勇気と、
変えられないものと変えるべきことを
見分ける知恵を、与えてください。
(後略)
ニーバーの祈り
人生には、私たちの力ではどうにもならない事柄が、たくさんあります。
地上での人生を見た場合、人生は決して公平ではありませんし、たいていの人が歩む道のりは、平坦で真っ直ぐなものではありません。
しかし結局のところ、自分に配られたカードを静かに受け入れ、その「持ち札」を使って勝負するしかないのです。
大切なことは「ニーバーの祈り」にあるように、
「変えられないもの」と「変えるべきこと」をゴッチャにしないことです。
ぜひ私たちは「変えられないもの」に不平不満を言い続け、力を浪費するのではなく「変えるべきこと」に目を向け、力を注ぎましょう。
仕事のストレスが辛い時の「一般的な対処法」【9選】
 K
K《 目次:一般的な9つの対処法 》
- 質の良い、十分な睡眠時間をとる習慣をつける。
- 新しい趣味を見つける等、自由な時間の充実を図る。
- 運動(スポーツ)をする習慣を取り入れる。
- 上司に直接相談してみる。
- 家族・友人・同僚等に相談してみる。
- 行政機関の相談窓口等を利用する。
- 専門医によるカウンセリングを受ける。
- 転職を検討する。
- 独立してフリーランスを目指す。
①【質の良い、十分な睡眠時間をとる習慣をつける】
これを1番はじめに持ってきた理由は、最も基本的且つ、重要なことでありながら、おろそかにされがちな対処法だからです。
様々な条件下のもとで、十分な睡眠時間を確保するのが難しい方もいることでしょう。
しかし、「SNS」や「テレビ」「動画」を見る等の時間を削ってでも、”規則正しい十分な睡眠の時間” は確保すべきです。
「睡眠」=「傷付いた心身を回復する時間」だからです。
②【新しい趣味を見つける等、自由な時間の充実を図る】
睡眠時間を徹底的に確保する習慣をつける一方で、仕事以外の時間を充実させることに意識を向けてみましょう。
何か新しい「趣味」をはじめるのでも良いですし、興味のある「活動」に参加するのも良いかもしれません。
また、プライベートの充実を図るための一環として、
「禁煙する」「ギャンブルをやめる」等、逆にこれまでの習慣を断つということも合わせて検討してみるとよいでしょう。
 K
K③【運動(スポーツ)をする習慣を取り入れる】
プライベートの充実を図りつつ、日々の生活に、あるいは休日などに「汗を流す習慣」を取り入れるようにしましょう。
男性であれば「筋トレ」がオススメです。筋トレは精神衛生上、非常に良い効果をもたらすとも言われています。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
また「筋トレは、ちょっとハードル高いなぁ……」という方は、
通勤時、駅までの道のりを歩くようにするだけでも良いので、とにかく何らかの形で、体を動かす習慣を付けてみましょう。
④【上司に直接相談してみる】
「生活習慣を変えるだけじゃ埒が明かない」という場合には、一か八か直球勝負で、上司に相談してみましょう。
もちろん「上司の人柄」や「あなたに対する評価」「職場環境」などにもよりますが、誠実に伝えれば…… 、
- 仕事量を減らしてもらえる。
- 業務の効率化を図ってもらえる。
- 他部署への異動を検討してもらえる。
等の可能性が全くゼロとは言い切れません。
⑤【家族・友人・同僚等に相談してみる】
「上司に相談してもムダだった……」ということであれば、信頼できる周囲の人に意見を聞いてみましょう。
 K
K⑥【行政機関の相談窓口等を利用する】
厚生労働省のホームページなどを見ると、全国にある相談窓口を調べることができます。
周囲に相談できる相手が誰もいない場合などには、利用を検討してみると良いでしょう。
⑦【専門医によるカウンセリングを受ける】
精神的に追い詰められている状況であれば、専門医によるカウンセリングも検討してみるべきかもしれません。
産業医のいる職場であれば、その方に相談するという形になるでしょう。
場合によっては「時短勤務」「休職」などの選択肢も考慮すべきです。
健康あっての仕事、健康あっての人生であることを、どうか忘れないでください。
⑧【転職を検討する】
ここまでご紹介したものをはじめ、考えうる対処法をすべて試し、それでも道が開けそうもないのであれば、その時はじめて「転職」について考えるべきでしょう。
 K
K
特に、もし、今のあなたの職場が、
- 長時間労働を強いられ、休暇もろくに取れない。
- 「求人に掲載されていた情報」と「実際の雇用条件」に相違がある。
など、いわゆる「ブラック企業」である場合には、自分の人生、もっと言えば「自分の命」を守るために「転職」という選択肢を検討してみるべきでしょう。
また、実際に転職しなくとも「転職先はいくらでもある」「転職しようと思えば、いつでもできる」という思いが自分の内にあるだけで、気持ちに余裕が生まれるものです。
 眠れる羊くん
眠れる羊くん
参考:【しんどい、もう無理】助けを求めるあなたに提案する”究極の逃げ道”
ですから、転職する・しないは別として、求人に目を通してみるだけでも気持ちが少しは楽になるかもしれません。
そして仮に、自分の希望に沿うような会社が運良く見つかったならば、その時、実際に行動を起こしてみるということも考えてみてはいかがでしょうか?
また、「1人では不安……」という方には、無料で転職をサポートしてくれる「転職エージェント」というサービスもオススメです。
⑨【独立してフリーランスを目指す】
最後にご紹介する対処法は「独立」です。
「独立」にも様々な形があるかと思いますが、特に、組織に馴染むのが苦手な「一匹狼タイプ」の方には、やはり魅力的な働き方と言えるでしょう。
例えば、余計な人間関係のストレスもなく、通勤時間もない「在宅ワーク」のできる仕事に魅力を感じている人は、かなり多いのではないでしょうか?
今や、クラウドソーシングサービスを利用して仕事を受注することなどもできる時代です。
ただし、決して甘い世界でないことは、考慮しておくべきでしょう。
辛い仕事のストレスからあなたを助けてくれる「聖書の名言」

† 強く、また雄々しくあれ。恐れてはならない。
彼らのゆえにうろたえてはならない。
あなたの神、主は、あなたと共に歩まれる。
あなたを見放すことも、見捨てられることもない。
申命記 31:6(旧約聖書/新共同訳)
† 穴を掘る者は自分がそこに落ち、
石を転がせばその石は自分の上に返ってくる。
箴言 26:27(旧約聖書)
† 疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。
休ませてあげよう。
マタイによる福音書 11:28(新約聖書)
† 主に従う者たちは力を新たにされ、
鷲のように翼を張って上るであろう。
イザヤ書 40:31(旧約聖書)
まとめ
- 何の備えもなく「社会」へと出ていくことは、フラッとコンビニにでも行くような軽装で富士登山に行くようなもの。
- ”聖書の人生観を自分の内にインストールする” ということは、”登山用のさまざまな装備を整える” ようなものであり、様々なストレスに対する「耐性」を高めてくれる。
- 人生には時に、全力で逃げ出すべき時がある。健康を損ね、働けなくなってしまう事態だけは、何が何でも避けなければならない。
- 私たちは、神に頼って生きるように創られている。
- 心や体が限界を感じ、健康が損なわれようとしている時、そこから逃げ出そうとすることは「甘え」ではなく、人として自然な反応。
- ”悪に対して悪で報いる” ことは、聖書的にはとても低レベルな反応。
- 「変えられないこと」と「変えるべきこと」をゴッチャにしないことが、とても重要。前者は泰然として受け入れなければならない。
いかがだったでしょうか?
このブログでは、聖書を人生の土台として生きるため「聖書という書物が本当に信頼できるものなのか?」ということを探究しています。
「揺るぎない人生の土台を築きたい」と思われた方は、どうぞ、
当ブログの目的が書かれたページから、この探究の旅へと参加してみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。